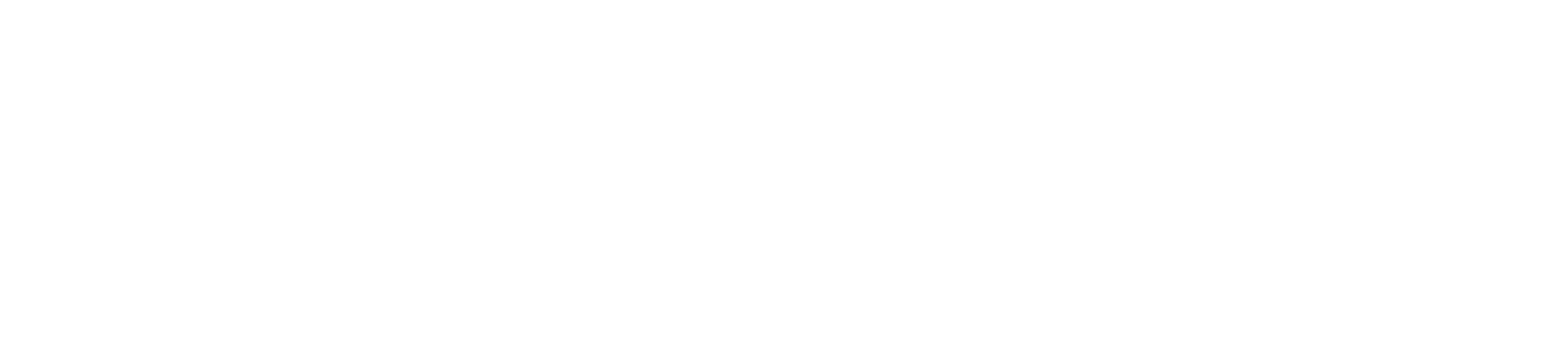本記事では、まずどちらを選ぶと失敗しにくいかを分かりやすく示し、その理由を人数・よく作る料理・台所の条件から説明しています。
パスタや具だくさんの汁物など、迷いがちな場面の答えも用意。
最後に、買う前のチェックリストと二本使いのコツで、今日すぐ決められるようにまとめました。
結論:18cm?それとも16cm?(一言で答えると…)
ひとつだけ買うなら18cmが無難です。余裕があるので吹きこぼれにくく、作り置きもこなします。
台所が狭い、軽さ重視、少量しか作らないなら16cmがラク。自分の普段作る量と、コンロの口の大きさ・収納場所・持てる重さなど台所の条件で選びましょう。
こんな人は16cmがラク
一人暮らしで汁物やソースを少しだけ作る人に向きます。
軽いので出し入れが簡単で、お湯がすぐ沸いて、洗うときも気になりにくいです。
インスタント麺、レトルトの温め、ココアやホワイトソースづくりなどの“小回り”が必要な場面で使いやすいと感じることが多いでしょう。
具を多く入れると縁まで近くなり、混ぜるときにこぼれやすくなるので、量を控えめにして火加減を落とすと安心です。
こんな人は18cmが安心
夫婦や二人暮らし、時々3人分まで作る人に向いています。
具だくさんの味噌汁、少量の煮物、カレーやシチューのミニ鍋、作り置きの下ごしらえまで幅広く利用できます。容量に余裕がある分、混ぜてもあふれにくく、茹でものも扱いやすいです。
重量は16cmより増えますが、日常の「これ一つで大体いける」という安心感が強く、最初の一本として失敗しにくい選択と言えます。
すぐ決めたい人のチェックリスト(人数×料理の目安)
- 1人で汁物やソース中心→16cmが手早く快適。
- 2人以上も作る、具を多く入れる、作り置きをしたい→18cmが安心。
パスタをよく茹でるなら18cmでも一人前は可能ですが、茹でやすさ優先なら別に大きめの両手鍋を用意すると、日々のストレスが減ります。
16cmと18cmの違いを3分で理解
大きな差は「余裕」です。18cmは同じ量でも縁までの高さが残りやすく、吹きこぼれと混ぜにくさを減らします。16cmは手軽に扱えお湯も速く沸きます。
用途が少量中心か、幅広く作るかで選ぶと迷いが減りますよ。
容量と“余裕度”の違い(味噌汁・スープ・カレー・パスタ)
鍋は入れられる量そのものより、「7~8分目で使えるか」が快適さを決めます。
18cmは同じ具量でも表面に余白が残るので、煮立ちの泡が盛り上がっても受け止めやすいです。味噌汁やスープは具が多いほど18cmの利点が出ます。
16cmは少量のソースや温め直しに最適ですが、カレーや煮物を“少し多め”に作ると混ぜにくくなります。
パスタは一人前なら18cmで対応できますが、余裕は小さめです。
取り回し・沸く速さ・洗いやすさ
軽さは正義です! 16cmは水も少なくて済み、加熱から沸騰までが速く、洗うときもシンク内で扱いやすいです。
18cmは面積が広い分、底に食材が広がり、炒め合わせやすく焦げつきにくい利点があります。重さは増えますが、ハンドルがしっかりしたものを選べば持ちやすさは確保できます。
日常で何を“毎日”するかを思い出すと、どちらの扱いやすさを優先すべきか見えてきます。
吹きこぼれと混ぜやすさの差
吹きこぼれは「加熱が強すぎる」「縁まで近い」の二つで起きます。
18cmは縁までの高さに余裕が出やすく、かき混ぜても波立ちにくいです。
16cmでも弱めの火にして、蓋を少しずらす、いったん火を落としてから味噌を溶くなどの工夫で防げます。
混ぜやすさは、鍋の直径と深さのバランスが大切です。18cmはヘラやおたまを動かす空間が増えるため、具を多めに入れる料理で使いやすく感じます。
人数・料理別の選び方
「何人分を何回を作るか」で決めると迷いがなくなります。少量中心なら16cm、2~3人や具だくさんが多いなら18cm。
よく作る料理を3つに絞って、それぞれで不足しないサイズを選ぶと失敗が減ります。
一人暮らし(少量・汁物中心)のベスト
一人分の味噌汁、スープ、麺、レトルト温めが主なら16cmが良いでしょう。
短い時間でつくる朝食や夜食でも負担が少なく、出し入れも簡単です。作り置きをほとんどしない、鍋を持ったまま注ぐ場面が多い、シンクが小さいなどの条件にも合います。
ただ、来客時や“自分+もう一人”の場面が月に何度かあるなら、18cmを選ぶと余裕が生まれます。迷うなら16cm+大きめ両手鍋の併用も現実的です。
夫婦・二人暮らし(具だくさん・作り置きあり)のベスト
日々の味噌汁を具たっぷりで作る、煮物を少量仕込む、カレーを二日分だけ作る――こうした場面は18cmがこなしやすいです。
混ぜても縁からこぼれにくく、再加熱のときにも安定します。
16cmは副菜やソース用として残し、主菜や汁物は18cmに任せると台所仕事が滑らかになります。
二人分の麺を頻繁に茹でる場合は、別に大きめの両手鍋を“麺専用”にするとさらに快適です。
3人以上の家庭・作り置き派の考え方
18cmでもサブ鍋としては便利ですが、主菜や汁物を家族分まとめて作るなら、もう一回り大きい鍋も検討すると安心です。
18cmは下茹でや副菜、離乳食の取り分け、小分けの作り置きに活躍します。
日常のメインは大きい鍋に任せ、18cmは手早く回す――この役割分担にすると、コンロの混雑も減って段取りが良くなります。
キッチン事情で変わる最適解
台所の条件に合わない鍋は、良い道具でもストレスになります。
使うコンロ、置き場、取り出しやすさを先に確認しましょう。重さやハンドル形状などの“持ちやすさ”も、毎日の使い心地を大きく左右します。
IH/ガスの「底径」適合をチェック
まず平たい底の直径を測ります。これを「底径」と言います。IH(電磁調理器)は、底径が小さすぎると反応しにくい機種があります。
取扱説明書の「使用できる鍋の大きさ」を確認しましょう。ガスも、炎が鍋底から大きくはみ出すと持ち手が熱くなります。
18cmは多くの口に合いますが、16cmは底が小さい製品もあるので実寸を確認すると安心です。
収納スペースと重さ(素材の違いもふくめて)
鍋の素材で重さが変わります。アルミは軽く、ステンレスは中程度、鋳物は重くなります。
取り出しやすい棚やコンロ下に置けるか、実際の動線を思い描きます。
16cmは重い素材でも扱いやすく、18cmは軽めの素材を選ぶと毎日が楽です。
水を入れると重さは一気に増えます。満水で持ち上げる場面があるなら、握りやすいハンドルとしっかりした蓋つまみを選ぶと安心です。
注ぎやすさ・目盛・フタの使い勝手
注ぎ口があると、汁物や麺の湯切りでこぼしにくくなります。
内側の目盛は水量を量る手間を減らします。
ガラス蓋は中の様子が見えて便利ですが、重さが増えます。金属蓋は軽くて扱いやすいです。
日々の使い方(注ぐ、量る、のぞく)の頻度を思い出して、必要な機能を優先すると、サイズの差以上に満足度が上がります。
迷いやすいシーン別の答え
判断に迷う場面を先に決めておくと、選択が速くなります。
パスタ一人前、具だくさん汁物、ソース・離乳食など、よくある3シーンで考えると、自分の正解がはっきりします。
パスタ1人前をよく作るなら?
18cmなら一人前のパスタを茹でられます。
湯量はやや控えめになりがちなので、吹きこぼれを避けるために火加減をやや弱めにし、麺を入れた直後は底に張り付かないようにしっかり混ぜます。
快適さや茹でやすさを最優先するなら、大きめの両手鍋を別に用意すると失敗が減ります。
16cmはスープパスタやショートパスタなど、少量で工夫する料理に向きます。
具だくさん味噌汁・スープはどっち?
根菜や豆腐、きのこをたっぷり入れるなら18cmが扱いやすいです。具を混ぜても縁からあふれにくく、味噌を溶くときに火を弱めれば吹きこぼれにくくなります。
16cmでも作れますが、具を控えめにしないと混ぜにくく感じます。
家族分をまとめて作る日が多いなら、18cmを“日常の汁物用”にするのが失敗しにくい選び方です。
ソース・離乳食・レトルト温めはどっち?
少量を手早く作るなら16cmが便利です。
ホワイトソースやカスタード、離乳食やジャムなど、焦げやすい料理は小さな火でじっくり混ぜたい場面が多く、鍋が軽いほど手が疲れません。
片口(注ぎ口)があると、ボウルや保存容器に移しやすく、こぼれを減らせます。
18cmは量を少し増やしたいときに向きますが、少量だけなら16cmの軽快さが際立ちます。
1本でいく?2本で使い分ける?
最初は1本で十分ですが、台所に狭くなければ2本にすると調理がスムーズになります。
18cm+16cmで役割を分けると、同時調理や作り置きがラクになります。自分の頻度の高い料理から決めましょう。
「まず18cm、あとで16cmをサブ」の理由
18cmは“外しにくい一本”です。汁物、煮物、下茹で、小さめの麺まで広く対応し、家族が増えてもサブとして残せます。
使いこなしてから、ソース用や少量の温めに強い16cmを足せば、毎日の段取りが良くなります。
2本体制にすると、汁物を温め直しながら副菜を作る、といった並行作業がしやすくなり、平日の調理時間を短くできます。
16cmメイン派が買い足すならどんな18cm?
軽くて深め、内側に目盛があり、注ぎやすい形が便利です。長めで握りやすいハンドル、がたつきにくい蓋も日常で効きます。
素材は日々の負担を考えて、総重量が無理なく持てるものを選びましょう。
16cmをソースや副菜専用にし、18cmを汁物や下茹でに回すと、同時進行の幅が広がります。
買う前のチェックリスト(失敗しないために)
購入前に3分だけ準備すると、サイズ選びで迷いにくくなります。
よく作る料理、使うコンロ口と底径、置き場所、持てる重さを紙に書き出します。
条件がはっきりすると、自分に合うサイズが自然に決まります。
今週よく作る料理を書き出す
味噌汁、スープ、煮物、麺、ソース、温め直し――この中で頻度の高いものを3つ選びます。
各料理でどのくらい作るか(1人、2人、3人)も書きます。
頻度と量がわかれば、必要な“余裕度”が見えてきます。例えば「味噌汁を2人分で具多め」なら18cm寄り、「ソースや温め直し中心」なら16cm寄り、と判断がしやすくなります。
よく使うコンロ口と鍋の底径を測る
底の直径をメジャーで測ります(これを底径と呼びます)。
IHは小さすぎる底径だと加熱しにくいことがあります。
ガスは炎が鍋底からはみ出さない範囲だと扱いやすいです。
よく使う口のサイズを把握しておくと、16cmでも18cmでも“ちょうど良く”乗る鍋を選べます。迷ったら、底面が広く安定するタイプを選ぶと失敗が減ります。
収納場所と出し入れの動線を確認する
鍋の置き場所、取り出すときの手順、戻す位置を実際に想像します。
ワンアクションで出せる棚に置けるか、フタをどこに置くか。
16cmは狭い棚にも入りやすく、18cmは積み重ねると取り出しにくいことがあります。
重ねる場合はフタのつまみ高さもチェックします。ラクに出し入れできるサイズこそ、毎日使い続けられます。
素材(ステンレス・アルミ・鋳物)の重さを想像する
素材名を難しく考えず、「持って苦にならないか」で判断します。
アルミは軽く、ステンレスは中くらい、鋳物は重い傾向です。
16cmは重い素材でも扱いやすく、18cmは軽めの素材を選ぶと動作が軽くなります。
水や具を入れると重さは増えます。満水で持ち上げる場面があるなら、ハンドルの太さや握りやすさも一緒に確認しましょう。
価格やブランドより“使い勝手”を優先する理由
毎日使う道具は、使いやすさが満足度を決めます。
安さや見た目だけで選ぶと、焦げやすい、注ぎにくい、しまいにくいなど、小さな不満が積み重なります。
自分の調理の流れに合うかどうかを最優先にしましょう。
安さだけで選ぶと起きやすい失敗例
底が薄すぎて焦げやすい、注ぎ口がなくてこぼす、蓋ががたついて湯気が目に入る――こうした小さな困りごとは、毎日の調理時間を確実に増やします。
価格差より、手に持ったときの安定感、ハンドルの握りやすさ、内側目盛の有無など、使い勝手に直結する点を優先すると、結果的に長く使えます。
長く使うための手入れのしやすさ
洗いやすい形か、汚れが溜まりにくい継ぎ目か、蓋と本体の段差はないか。
毎日の洗い物でストレスが少ない形を選ぶと、自然と手入れが続き、長持ちします。焦げついたときの対処法がシンプルかどうかも確認します。
道具に気を遣いすぎないことが、長く付き合う近道です。
迷ったらこの組み合わせ(おすすめ例)
はじめての一本は18cmで“外しにくい”。二本目は16cmで“軽快に”。
この組み合わせにすると、同時調理や作り置きが楽になり、平日の自炊が安定します。
自分の台所に合わせて、素材や重さを調整しましょう。
最初の1本に向く18cmのタイプ
軽めでやや深め、注ぎやすい形、内側目盛つき、安定する蓋。
この条件がそろうと、汁物、煮物、下茹で、麺まで広く対応できます。
ハンドルは熱くなりにくく、握りやすいものを。重さが気になるなら、軽い素材を選ぶと毎日の負担が減ります。
最初の一本に迷ったら、この方向性が失敗しにくいです。
2本目に便利な16cmのタイプ
ソース、温め直し、離乳食、少量の麺に強い軽快な一本。
片口や小さめの注ぎ口があると移し替えがスムーズです。シンクで洗いやすく、朝の短時間調理にも向きます。
18cmと重ならない役割を意識して選ぶと、台所の回転が良くなります。収納場所が狭い人にも適します。
よくある質問(Q&A)
よくある疑問を先に解決しましょう。サイズを決める最後の後押しに使ってください。
迷ったら、普段作る量を基準に「余裕が残る方」を選ぶと失敗が減ります。
16cmで2人分は作れる?
汁少なめ・具控えめなら作れますが、縁まで近くなりやすく、混ぜるときにこぼれやすいです。
具だくさんにしたい日や、翌日の分も少し残したい日は18cmが快適です。
16cmで作るときは、火加減を弱め、調味を段階的にして沸き上がりを抑えると安心です。
18cmでパスタは無理?
一人前なら可能です。湯量が少なめになるので、沸騰直後は火力を少し落とし、麺を入れた直後に底からよく混ぜます。
ふきこぼれを避けるため、蓋をせずに茹でると扱いやすいです。茹でやすさを最優先するなら、別に大きめの両手鍋を用意すると失敗が目に見えて減ります。
小さい鍋でも吹きこぼれにくくするコツは?
“強火のまま放置しない”が基本です。
加熱は中火までにし、沸いたら弱めます。蓋は少しずらして湯気の逃げ道を作ります。
味噌やとろみを加える前にいったん火を弱めると、泡が持ち上がりにくくなります。
鍋の7~8分目で使うと失敗が減ります。
これだけで日常のストレスがかなり減ります。
まとめ
結論は「一本なら18cm、少量中心なら16cm」。違いは“余裕”と扱いやすさです。
人数と普段作る量、コンロや収納などの条件で選べば迷いません。パスタ一人前は18cmで可、茹でやすさ重視は両手鍋を別に。
また、購入前の確認ポイントと、18cm+16cmの使い分けも紹介しました。
- 人数・料理で選ぶ早見表
- 取り回し・吹きこぼれの差
- 台所の条件(底径・収納・重さ)
- 迷いがちな場面の答え
- 失敗しないチェックリスト